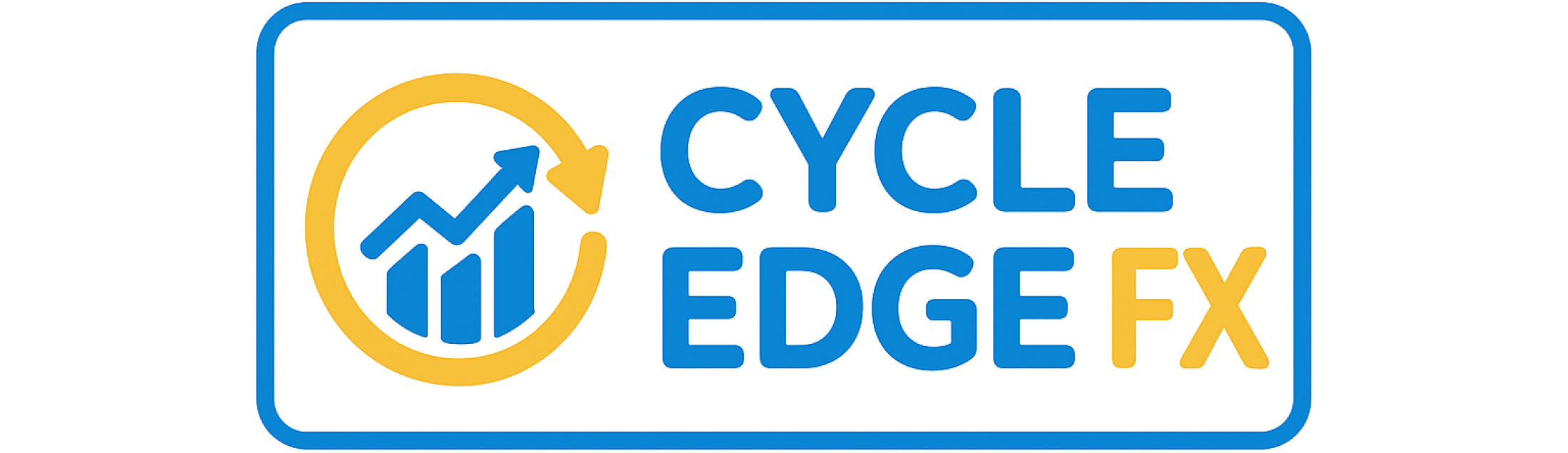なぜダウ理論を利用するのか
なぜ、ダウ理論なのでしょうか。
トレードを始めようとする方であれば一度は聞いたことがある理論だと思います。
実際利用している人もいるでしょう。
だけど、なんとなく、聞いたことがあるけど古い理論だから使えない、当たり前すぎるなどの理由で敬遠されがちなのも事実です。
なぜ、ダウ理論なのか。
あなたは現在何をもとにトレードを行なっていますか?
・上げそうだから
・ゴールデンクロスになったから
・ミラートレード・・・
様々だと思います。
では、トレンドをどのように認識していますか?「トレンドに乗る」などと言われていますが、そもそもトレンドとはなんでしょうか。
上昇トレンドの場合は、上昇時間が下落時間よりも長く、上昇する値幅は下落する値幅よりも大きくなることが多い。
そしてこれを理論立てて、今の相場がどのような環境に位置しているのか、どの様なトレンドが発生しているのか、それを表現しているのがダウ理論です。
ダウ理論で有名な理論は
「隣り合う高値、安値が切り上がればアップトレンド」
本などでも読んだことがあると思います。
一言で言ってしまえばそれまでです。読んだ人にとっては
「だからなんだ?」
で終わってしまいかねないです。 しかし、実はここには大きなヒントが隠されているのです。
アップトレンド・ダウントレンドという環境認識は、使用している手法によって人それぞれですが、ダウ理論の場合、「隣り合う高値、安値が切り上げ続ける限りアップトレンド」と定義づけられます。
しかし、この意味を深く理解していないと全く使う気にはなれないでしょうし、ある意味、当たり前すぎて活用されない理論になっているのが現状です。
「今はダウ理論が完成しているから買いだな。」
などと、自分がエントリーしたい時だけ都合よくつかわれたりします。
ダウ理論を「知っている」だけ、古典的な理論で今は機能していないから、もっと洗練された手法や格好いいルールの方がいい、などと見向きもされないことのほうが多いです。 「知ってる」だけではなく、「理解して活用する」理論に変えるために、これからお伝えしていきます。
「隣り合う高値、安値が切り上がるのがダウ理論だ。」 そう覚えたり、なんとなく分かることは簡単です。
でも、なぜそうなるとアップトレンドなのか?それを理解しないと納得してトレードしたり、この相場の本質の理論を使いこなすこともできません。
ダウ理論にはどんな優位性が含まれているのか、これを紐解いていけばそこには当たり前だけど、驚くべき真実が隠されているのです。
では一つ一つ、優位性がある根拠を明確にしていきます。
ダウ理論とは
ダウ理論とは、19世紀の経済学者チャールズ・H・ダウの没後、彼が『ウォール・ストリート・ジャーナル』紙に書いた論説が基になっており、株や先物、為替の成功法則として広く知られているものです。
19世紀に発見された理論が未だに語り継がれている、という事実が人の集団心理は不変なのだと証明しています。
ダウ氏が展開した理論を紹介します。
ダウ理論とは(一部抜粋)
(1)「相場にはトレンドというものが存在し、何かの出来事が起きない限り、継続する」
(2)「相場には3つのトレンドがあり、資産保全の意味では長期トレンドを意識していればよく、難しいのは訂正トレンドの予測を的確にして、確実に儲けること」
(3)「最高値と最低値が連続して上昇するときは上昇トレンドになり、連続して下降するときには、下降トレンドとなる」
(1)、(2)も重要ですが、今回は(3)を見ていきます。
一番有名な部分だと思います。(3)「最高値と最低値が連続して上昇するときは上昇トレンドになり、連続して下降するときには、下降トレンドとなる」わかるようでわからないし、とても当たり前のように思える。言葉だけで理解しようとするととてもわかりづらいですね。
下の図を見てみましょう。

①と③を安値、②と④を高値とすると、「最高値と最低値が連続して上昇するときは上昇トレンドとなる」とは上の図のような形になるということです。
左の安値よりも次の安値の方が切り上がり、左の高値よりも次の高値の方が切り上がっていれば、どう考えても上昇していきますよね。
そして、この高値と安値が連続して上昇していく限りアップトレンド、となります。当たり前ですねぇ~。ダウントレンドの場合の図も載せておきます。

①と③を高値、②と④を安値とすると、「最高値と最低値が連続して下降するときには、下降トレンドとなる」ということになります。
こちらもどう考えても下落していきますよね。そして、これが続いていく限りダウントレンド、ということになります。簡単ですね。
でも、奥が深いんです。もちろん、これだけでは終わりません。それをこれからひも解いていきます。
ダウ理論について一般書籍で語られているのは上記までの内容がほとんどです。
そして「こんな考え方もあるんだよ~」といったさわりとして紹介されているモノばかりです。
でも本書ではダウ理論がメインでお伝えしたいことの一つとなっています。
ここからは、他ではなかなか知ることができない、価値の高い情報を提供していきます。
ダウ理論の使い方
ダウ理論のことはわかったし、むしろ知っていた、という方がほとんどだと思います。
参考にはしていた、という方はいると思いますが、ダウ理論でトレンドを認識し、トレードしていた、という人は少ないのではないでしょうか?
実際には理論を突き詰めていかないと、結局知っている、理解しているだけでは何もできません。
では、この理論をどう活用していけばいいのでしょうか。
そもそもどのタイミングで入るのがいいのか?下の図を見てください。

先程の図に手を加えたものです。それぞれの赤丸は、「①の安値からの反発」「③のからの反発」「②の高値(前回の高値)を切り上げる」
ダウ理論を利用してエントリーする場合、上記3つのタイミングでエントリーすることが可能です。
逆に言えば、ほかのタイミングでの入り方を私は知りません。
では、どのタイミングでエントリーするのがより勝つ確率が高いのでしょうか?
どこでエントリーすればよいのか
それは「②の高値を切り上げる」→「③のからの反発」→「①の安値からの反発」の順番でより優位性の高いエントリーができる、
ということが言えます。では、それぞれ見ていきましょう。
「②の高値を切り上げる」このポイントでの買いエントリーは高値、安値が切り上がったことが判明した瞬間です。
ですので、ダウ理論が完成した瞬間。ダウ理論でいえばもっとも失敗の少ないエントリータイミングとなります。
「③の安値からの反発」③からの反発は、ダウ理論が完成するであろうと仮定し、買いエントリーするポイントになります。
安値は切り上げていますが、この段階では高値の切り上げは確認できず、ダウ理論は完成していないため、あくまでも高値を今後超えていくだろうと仮定してエントリーすることになります。
そして、「②の高値を切り上げる」よりは上昇していく可能性は少なくなります。「①の安値からの反発」まだ、ダウントレンドが継続中です。
トレンドの転換を疑って買いエントリーとなりますが、安値、高値共に切り上げておらず、3つの中では一番優位性の低いエントリーとなります。
ただし、このポイントは今後のシリーズでお伝えするサイクル理論を組み合わせることでより優位性高くエントリーすることもできます。
以上はダウ理論の基本ですが、もう一つ高値、安値の切り上げのパターンを紹介します。
下図、「例1」は、先程お伝えした形ですが、「例2」は最初に高値を切り上げるパターンです。

例2の場合、「②の安値からの反発」「①の高値を切り上げる」「④の安値からの反発」の3つのエントリーポイントがあります。
より優位性の高い順番は「④の安値からの反発」→「①の高値を切り上げる」→「②の安値からの反発」の順番になります。
④が確定した時点で高値、安値の切り上げが確定し、ダウ理論の完成となります。
では、ダウ理論が実際にどのように形成されているのか、実際のチャートで確認してみましょう。